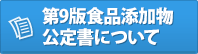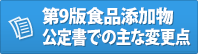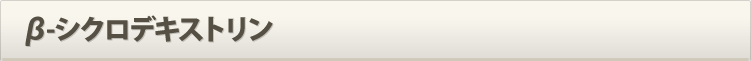定 義
本品は、デンプンを酵素処理し、非還元性環状デキストリンとして得られたものであり、シクロデキストリンのうち7個のD-グルコース単位からなる環状オリゴ糖である。
含 量
本品を乾燥したものは、β-シクロデキストリン(C42H70O35)98.0%以上を含む。
性 状
本品は、白色の結晶又は結晶性の粉末で、においがなく、わずかに甘味がある。
(ただし、性状の項目の形状は、参考に供したもので、適否の判定基準に示すものではない。)
確認試験
本品0.2g(0.15~0.24g)にヨウ素試液2ml(駒込ピペット使用)を加え、水浴中で60~70℃に加温して溶かした後、室温(1~30℃)に放置するとき、黄褐色の沈澱を生じる。
純度試験
- (1)比旋光度 [α]20D=+160~+164°
- 本品を乾燥し、その約1g(0.9~1.1gを0.1mgまで量り取る)を精密に量り、水を加えて正確に100ml(メスフラスコを使用)とし、30分以内に旋光度を測定する。
β-シクロデキストリンの溶解度は低い(室温で約2%W/W)ため、完全溶解を確認の上、測定する。
乾燥条件は、105℃、0.67kPa以下、4時間以上で行う。(乾燥減量後のサンプルを使用) - (2)溶状
- 無色、澄明(0.50g、水50ml)(0.495~0.504g、メスシリンダー使用)
- (3)塩化物 Clとして0.018%以下(0.50g、比較液 0.01mol/L 塩酸0.25ml)(0.495~0.504g、メスピペット使用)
- 被験物質 0.50gを量り、ネスラー管に入れ、蒸留水約30mlを加えて溶かし、液がアルカリ性の場合は、硝酸(1→10)を加えて中和し、更に硝酸(1→10)6ml及び蒸留水を加えて50mlに定容し、検液とする。
別のネスラー管に0.01mol/L 塩酸0.25mlを量り、硝酸(1→10)6ml 及び蒸留水を加えて50mlに定容し、比較液とする。検液が澄明でない場合は、両液を同じ条件でろ過する。
検液及び比較液に硝酸銀溶液(1→50)1mlずつを加えてよく混和し、直射日光を避け、5分間放置した後、両ネスラー管を黒色を背景とし、側方及び上方から観察して濁度を比較するとき、検液の呈する濁度は、比較液の呈する濁度より濃くない。 - (4)重金属 Pbとして5.0μg/g以下(4.0g、第2法、比較液 鉛標準液2.0ml)(3.95~4.04g、メスピペットを使用)
- 石英製又は磁製のるつぼに被験物質4.0gを量り、弱く加熱して炭化する。放冷後、硝酸2ml 及び硫酸5 滴を加え、白煙が生じなくなるまで加熱した後、450~550℃で灰化するまで強熱する。放冷後、塩酸2mlを加え、水浴上で蒸発乾固し、残留物に塩酸3滴及び熱湯10ml を加え2分間加温する。放冷後、フェノールフタレイン試液1 滴を加え、アンモニア試液を液がわずかに赤くなるまで加えた後、蒸留水を用いて定量的にネスラー管に移す。更に酢酸(1→20)2 ml及び蒸留水を加えて50mlに定容し、検液とする。別に被験物質の場合と同質のるつぼに硝酸2ml、硫酸5滴及び塩酸2mLを入れ、加熱して蒸発乾固し、残留物に塩酸3滴を加え、以下検液の調製の場合と同様に操作して定量的に別のネスラー管に移す。更に鉛標準溶液2.0ml、酢酸(1→20)2ml及び蒸留水を加えて50mlに定容し、比較液とする。
検液が澄明でない場合は、検液及び比較液を同一条件でろ過する。
検液及び比較液に硫化ナトリウム試液2 滴ずつを加えて混和し、5分間放置した後、両ネスラー管を白色の背景を用い、上方及び側方から観察するとき、検液の呈する色は、比較液の呈する色より濃くない。 - (5)鉛 Pbとして1.0μg/g以下(10.0g、第1法)(9.95~10.04g、一般試験法18.重金属試験法参照)
- 白金製又は石英製のるつぼに被験物質10.0gを量り、少量の硫酸で潤す。徐々に加熱して、できるだけ低温でほとんど灰化後、放冷し、更に硫酸1mlを加え、徐々に加熱して450~550℃で灰化するまで強熱する。残留物に少量の硝酸(1→150)を加えて溶かし、更に硝酸(1→150)を加えて、10mlに定容し、検液とする。比較液として鉛標準溶液1.0mlを量り、硝酸(1→150)を加えて、10mlに定容し、比較液とする。
検液及び比較液につき、次の条件で原子吸光光度法(フレーム方式)により吸光度を測定するとき、検液の吸光度は、比較液の吸光度以下である。
- 光源ランプ:鉛中空陰極ランプ
- 分析線波長:283.3nm
- 支燃性ガス:空気
- 可燃性ガス:アセチレン
- (6)ヒ素 As2O3として1.3μg/g以下(1.5g、第2法、装置B)(1.45~1.54g、一般試験法35.ヒ素試験法参照)
- 小ビーカーに被験物質1.5gを量り、蒸留水5ml、硫酸1mL及び亜硫酸10mlを加えた後、水浴上で加熱する。亜硫酸がなくなり、約2ml程度になるまで蒸発し、蒸留水を用いて5mlに定容し、検液とする。
検液を発生瓶に入れ、ブロモフェノールブルー試液1 滴を加え、アンモニア水、アンモニア試液又は塩酸(1→4)で中和し(*1)、塩酸(1→2)5ml及びヨウ化カリウム試液5mLを加え、2~3分間放置後、酸性塩化第一スズ試液5mlを加えて10分間放置後、蒸留水を加えて40mlとする。この液にヒ素分析用亜鉛2gを加え、装置Bを用いてヒ化水素吸収液5mlに吸収させる。1 時間放置後、吸収管をはずし、必要があればピリジンを加えて5mlとし、吸収液の色を観察するとき、この色は、次の標準色より濃くない。なお、535nmにおける吸光度も測定しておく。
標準色の調製は、ヒ素標準溶液2.0mlを発生瓶に量り、*1以降の操作を検液の調製と同時に行う。
以下に装置Bの図を示した。 - (7)還元物質
- 本品を乾燥し、その1.0g(0.95~1.04g)を正確に量り、200ml容ビーカーに入れ、水25ml(メスシリンダーを使用)を加えて溶かし、フェーリング試液40ml(メスシリンダーを使用)を加え、3分間穏やかに煮沸する。冷後、沈澱がなるべくフラスコ内に残るように注意しながら、上澄液をガラスろ過器(1G4)を用いてろ過し、沈澱を温水(60~70℃)で洗液がアルカリ性(pH試験紙またはフェノールフタレイン試液を使用)を呈さなくなるまで洗い、洗液を先のガラスろ過器を用いてろ過し、ろ液は捨てる。沈澱に硫酸第二鉄試液20ml(メスシリンダーを使用)を加えて溶かし、これを先のガラスろ過器を用いてろ過した後、水洗し、ろ液及び洗液を合わせ、80℃に加熱し、0.02mol/L 過マンガン酸カリウム溶液で滴定するとき、その消費量は3.2ml以下である。
乾燥減量
14.0%以下(105℃、0.67kPa以下、4時間)(一般試験法9.乾燥減量試験法参照)
あらかじめ秤量瓶を減圧下(0.67kPa以下)105℃で約30分間乾燥し、デシケーター中で放冷した後、その質量を精密に量る。被験物質1~2gを先の秤量瓶に入れ、広げた後、その質量を精密に量る。次にこれを乾燥器に入れ、減圧下(0.67kPa以下)で105℃、4時間乾燥する。デシケーター中で放冷した後、その質量を精密に量る。乾燥後の被験物質は吸湿しやすいので、秤量等の操作は素早く行なう。
| 乾燥減量(%)= | 乾燥前(秤量瓶+被験物質)質量(g)-乾燥後(秤量瓶+被験物質)質量(g) | ×100 |
|---|---|---|
| 被験物質質量(g) |
ガラスの秤量瓶は湿度の影響を受けやすいので乾燥が必要であるが、アルミの秤量皿を用いると、秤量瓶の乾燥工程は省略できる。
強熱残分
0.10%以下(550℃)(一般試験法12.強熱残分試験法参照)
白金製、石英製又は磁性のるつぼを550℃で、約30分間(恒量になるまで)強熱し、素早く電気炉より取り出しデシケーター中で放冷後、その質量を精密に量る。被験物質1~2gを先のるつぼに入れ、その質量を精密に量る。硫酸少量を加えて潤し、徐々に加熱して出来るだけ低温でほとんど灰化した後、放冷する。更に硫酸1mlを加え、徐々に加熱して硫酸の蒸気がほとんど発生しなくなった後、これを電気炉に入れ、550℃、3時間(残留物が恒量になるまで)強熱し、素早く電気炉より取り出し、デシケーター中で放冷した後、その質量を精密に量る。得られた値が規定値に達していない場合は、残留物が恒量になるまで強熱する。
| 強熱残分(%)= | (強熱残留物+るつぼ)質量(g)-るつぼ質量(g) | ×100 |
|---|---|---|
| 被験物質質量(g) |
乾燥後の被験物質は吸湿しやすいので、秤量等の操作は素早く行なう。
定 量 法
本品を乾燥(乾燥条件は105℃、0.67kPa以下、4時間。 乾燥減量後のサンプルを使用)、その約0.5g(0.45~0.54gを0.1mgまで量り取る)を精密に量り、50ml容メスフラスコに入れ、加熱した水(特に規定しないが60~80℃の温水を使用すると容易に溶解)約35ml(メスシリンダーを使用)を加えて溶かし、冷後(水冷または空冷)、水を加えて正確に50ml(メスフラスコを使用)とし、検液とする。別に定量用β-シクロデキストリンを乾燥し(乾燥条件は105℃、0.67kPa以下、4時間。乾燥減量後のサンプルを使用可能)、約0.7g(0.65~0.74gを0.1mgまで量り取る)を精密に量り、50ml容メスフラスコに入れ、加熱(100℃)した水約45ml(メスシリンダーを使用)を加えて溶かし、冷後(水冷又は空冷)、水を加えて正確に50ml(メスフラスコ中)とし、標準液とする。更にこの標準液5ml(ホールピペットを使用)を正確に量り、水を加えてそれぞれ正確に10ml及び20ml(メスフラスコを使用)とし、標準液とする。検液及び3濃度の標準液をそれぞれ10μl(マイクロシリンジ、オートサンプラー)ずつ量り、次の操作条件で液体クロマトグラフィーを行う。濃度の異なる標準液それぞれのβ-シクロデキストリンのピーク面積を測定し、検量線を作成する。この検量線と検液のβ-シクロデキストリンのピーク面積から検液中のβ-シクロデキストリンの量(g)を求め、次式により含量を求める。
| β-シクロデキストリン(C42H70O35)の含量 = | 検液中のβ-シクロデキストリンの量(g) | ×100(%) |
|---|---|---|
| 試料の採取量(g) |
β-シクロデキストリンは吸湿性がある為、多湿時期の取扱いには注意が必要である。
操作条件
| 検出器 | 示差屈折計 |
|---|---|
| カラム充てん剤 | 9~10μmの液体クロマトグラフィー用強酸性陽イオン交換樹脂 |
| カラム管 | 内径 5~10mm、長さ20~50cmのステンレス管(公定書に内径10mmとあるが5~10mmで差支えない。) |
| カラム温度 | 50~80℃の一定温度 |
| 移動相 | 水 |
| 流量 | 0.3~1.0ml/分の一定量 |
具体的なHPLCの操作例
| 検出器 | 示差屈折計 |
|---|---|
| カラム | Bio-Rad社製Aminex HPX-42A(内径7.8mm、長さ30cm)S |
| カラム温度 | 80℃ |
| 移動相 | 水 |
| 流量 | 0.6ml/分 |
β-シクロデキストリンはピークの形状がブロードなため、ピーク検出条件は厳密に管理する。n=2で実施しているが、検出器にRIを使用しているため、面積値の誤差率が大きい時には、標準液と検液の分析n数を増やすことが好ましい。
オートサンプラーを用いる場合、βーシクロデキストリンのピーク面積の誤差を小さくする為、検液、標準液ともに蓋付ダーラム管を使用するか、分析直前にオートサンプラーにセットするなどして、検液、標準液の蒸発を防ぐとよい。
オートサンプラーを用いる場合、標準液は濃度の薄い液から分析を行うと検量線の誤差は小さくなる。
定量値の上限が100.5%以上となった場合は再度測定をやり直す必要がある。(乾燥が不完全でないか確認する)
カラムとしては三菱化学社 MCI GEL CK04S(内径:10mm*長さ:200mm←α-CD、γ-CDでは「内径7.8mm、長さ30cm」となっているが、どちらが正しい?、60℃、0.4ml/min)も実績がある。海外で使用されることの多いODSタイプのカラムは見かけ上純度が高くなる。
β-シクロデキストリン、定量用
(第8版食品添加物公定書 p104 C試薬・試液 1.試薬・試液)
C42H70O35 本品は、白色の結晶又は結晶性の粉末で、においがなく、わずかに甘味がある。
確認試験
本品0.2gにヨウ素試液2mlを加え、水浴中で加温して溶かした後、室温に放置するとき、黄褐色の沈殿を生じる。
純度試験
- (1)比旋光度 [α]20D=+160~+164°
- 本品を乾燥し、その約1g(0.9~1.1gを0.1mgまで量り取る)を精密に量り、水を加えて正確に100ml(メスフラスコを使用)とし、30分以内に旋光度を測定する。
- (2)類縁物質
- 本品約1.5g(1.45~1.54gを0.1mgまで量り取る)を精密に量り100mlのメスフラスコに入れ、温水約70ml(メスシリンダーを使用)を加えて溶かし、冷後(水冷または空冷)、水を加えて正確に100ml(メスフラスコを使用)とし、検液とする。この液1mlを正確に量り、水を加えて正確に100ml(メスフラスコを使用)とし、比較液とする。検液及び比較液20-100μl[検液20μl及び比較液100μlそれぞれの意? 同量だが量を範囲で規定する場合は、同量の旨を表記すべきでは](マイクロシリンジ、オートサンプラー)につき、次の操作条件で液体クロマトグラフィーを行い、ピーク面積を測定するとき、検液中の主ピーク以外のピークの合計面積は、比較液の主ピーク面積より大きくない。ただし、面積測定範囲は、主ピークの保持時間の2倍までとする。
操作条件
「β‐シクロデキストリン」の定量法の操作条件を準用する。
乾燥減量
14.0%以下(1.0g、105℃、0.67kPa以下、4時間)(一般試験法9.乾燥減量試験法参照)
上記試験について実施済みの市販標準品をその結果とともに入手し、使用する場合は省略することができる。
謝辞:本シクロデキストリン解説書はCD工業会が作成いたしました。作成に当たり(社)日本食品衛生協会 食品衛生研究所の監修を受け、同所の標準作業書の一部の転用許可を受けました。ここに厚く御礼申し上げます。